私家版 犹太文化论
第六届小林秀雄奖殊荣
著者自身が冒頭でことわっていますが、一般的な「ユダヤ人問題」概説書ではありません。
とはいえ、「ユダヤ人ってなに?」くらい無知な人以外は身構えて読まなければならないことはないです。
第二章・第三章がそれぞれ「日本人とユダヤ人」、そしてフランスにおける反ユダヤ主義と「最初 のファシスト」に当てられていて、反ユダヤ主義と陰謀史観を巡る知見を広める用にも足りますが、中心は第一章と第四章。著者の思考の核にあるのは、結局「ユダヤ人とは何か」という問いであり(そしておそらくそれにしか本当は興味がない)、サルトルとレヴィナスの「ユダヤ人観」の対置を通じて、「ユダヤ人」なるものを構造的に再発見しようという試みです。
この対置については、「はじめに」で非常に平易な形で触れられます。
「なぜユダヤ人は迫害されるのか」という問いに...
私家版 犹太文化论
第六届小林秀雄奖殊荣
著者自身が冒頭でことわっていますが、一般的な「ユダヤ人問題」概説書ではありません。
とはいえ、「ユダヤ人ってなに?」くらい無知な人以外は身構えて読まなければならないことはないです。
第二章・第三章がそれぞれ「日本人とユダヤ人」、そしてフランスにおける反ユダヤ主義と「最初 のファシスト」に当てられていて、反ユダヤ主義と陰謀史観を巡る知見を広める用にも足りますが、中心は第一章と第四章。著者の思考の核にあるのは、結局「ユダヤ人とは何か」という問いであり(そしておそらくそれにしか本当は興味がない)、サルトルとレヴィナスの「ユダヤ人観」の対置を通じて、「ユダヤ人」なるものを構造的に再発見しようという試みです。
この対置については、「はじめに」で非常に平易な形で触れられます。
「なぜユダヤ人は迫害されるのか」という問いに「ユダヤ人迫害には根拠がない」と答えるのは「政治的に正しい」ことですが、この回答は実のあることは何一つ得られず、議論は一歩も進展しません。もちろん「ユダヤ人迫害には根拠がある」という答えは「政治的に正しくな」く、単なる反ユダヤ思想です。それゆえ、「反ユダヤ主義には理由があると信じている人間がいることには理由がある」という一段メタなところから始めなければ、何も思考することができません。
この「政治的に正しいけれどそれを言ったところで何にもならない」言説の向こうに行こうとすることは非常に重要です。相対主義の「何も言えなさ」と一緒で、「良い人もいる、悪い人もいる」などとしたところで何にもなりません。そんなことはわかっています。
問題はこの向こうに一歩踏み出すとき、単なるバイアスではない方向へと進むことです。この一歩は、往々にして「わたしは・・・と思うよ」とか「・・・の方が好き」という、別の意味での「力ない」一歩になってしまいがちです(個人の自由だから参拝します、とかね)。そんなことは聞いていません。
実は「はじめに」でこの対置が提示された時点で、本書の主要なテーマが既にむき出しになっています。サルトルの主張というのは、要するに「『ユダヤ人』は反ユダヤ主義者が作り出したもの」ということですが(少なくともこのような思想を代表するものとしてサルトルが取り上げられている)、この言説は非常に非常に正しくも、肝心なところに手が届いていません。世の中にはこのサルトルの思考も理解できない人がいて、だからこそ彼も声を張り上げなければならなかったのですが、ここに留まっていては「政治的に正しいけれど何も言えない言説」から抜け出せません。
寄り道ですが、サルトルという人はつくづくこの手の「正しくキレイだけれど力ない」言葉にエネルギーを吸い取られてしまった方だと思います。こういう人はいてくれないと困ります。サルトルのお陰でその後の思想家が語りだせたことが沢山あります。ただご本人については本当にお気の毒で、その後の自己批判のしょんぼりとした様子など、痛々しくて見ていられません。かつて最初期のレズビアン・フェミニストが対抗陣営への反撃に消耗していったエピソードがありますが、どこかで「そんなことをやっているくらいならコミュニティの充実を図る方がマシ」という方向転換が必要になってきます。ただ、正にこの転換が、内にこもる形(「わたしは好き」「・・・と思う」)だけになってしまうのが一番危険なのですが。
さて、「『ユダヤ人』は反ユダヤ主義者が作り出したもの」とは、「ユダヤ人」にはそれ自体としての定義など存在せず(これは正しい)、反ユダヤ主義者の幻想が作り出したもの、ということです。それでいてなおユダヤ人共同体に統一があるのは、そのように名指された者の「状況」が彼ら独特の性質を生み出しているからです。つまりユダヤ人とはユダヤ人な「状況」に置かれた人びとであり、ユダヤ人の「ユダヤ人らしさ」も「状況」によるもの、ということです。
このロジックは、かなりの範囲で妥当です。少なくとも、「ユダヤ人」を何らかの属性(民族・人種・国家・宗教・・)に還元して考える人びとに対抗するには、まずこの理屈を持ってくる必要があります(日本には「ユダヤ人」とは「ユダヤ教徒」だと思っている人が多いような気がしますが、「ユダヤ人」は宗教にも還元できません『揺れるユダヤ人国家―ポスト・シオニズム』という本の冒頭には「自分はユダヤ人だが、無神論者だ」というイスラエル市民の声が紹介されています)。しかし決定的な見落としがあるゆえに、結局はperformativeな力を持っていません。それは「ユダヤ人/非ユダヤ人」という分節の始原について何も語れていない、という点です。
「女性」とは「女性」と呼ばれる人間のことであり、そのカテゴリーを作り出したのは、これにより社会的リソースを独占しようとする「男性」である。この(社会構築主義)ジェンダー論の常套句に、著者は疑問を挟みます。「性化された社会の起源において父権的な社会慣行を作り出したのは性的に誰なのか?」。
これは「ニワトリが先か卵が先か?」という問題ではありません。実際のところ家父長制を作り出したの者の染色体がXXであったかXYであったかなどということではなく、わたしたちがそのような分節(ユダヤ人/非ユダヤ人、男性/女性)を前提としてしか思考できない、ということです。ユダヤ人を巡る様々な言説、あるいは性差というものそのものが幻想であることは疑いの余地がありませんが、この幻想はわたしたちの思考の枠組み自体でもあるため、それ(通事的というより論理的に)「以前」を問うことができないのです。
わたしたちは「『男』抜きの『女』」というものを想像できませんし、しかもこの分節以後に男と女について何事かを言おうとすると、社会構築主義者のようにしか「正しく」語る方法がありません。著者は、このような分節の背後に隠されたシニフィアンがあり、ユダヤ人や男/女はこれを表象代理している、というラカンの論をひきます。代理されているのはシニフィエではなくシニフィアンです。世界の謎を一気に解決する「意味」があるのではなく、隠されたのはシニフィアンであり、それは既にないもの(世界の中には一度もなかったもの!)です。
これをわたしなりにパラフレーズしてみると、ユダヤ人とは世界の内部に存在するものではなく、世界そのものと共に(世界そのものに不可欠なものとして)産み落とされた、ということになります。ユダヤ人は、少なくともヨーロッパという世界の枠組みそのものの一部なのです。
わたしとしては、この時点でかなり満足してしまうのですが、著者はさらに問いかけます。「ユダヤ人のいる世界」への跳躍により、世界は何を手に入れたのか?と。
ここから先を引き受けるのは本書終章です。終章は第一章ほど「透明」ではありません。おそらく著者自身、バイアスと思われても仕方ない、くらいの覚悟をもって書かれたのではないかと思います。ここでの主な参照先はレヴィナスです。
レヴィナスはサルトルの(「正しい」)論を退け、ユダヤ人は「完全に神に見捨てられる」という例外的体験のもとに選ばれた、とします。ただし「選ばれた」ことが意味するのは特権ではなく有責性です。「ユダヤ人は非ユダヤ人より世界の不幸について多くの責任を引き受けなければならない」。この責任とは、やってもいないことについての責任が、自身に先立って課せられている、ということです。
内田樹:1950年東京生まれ。思想家。神戸女学院大学名誉教授。凱風館館長。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。2007年『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)で第6回小林秀雄賞を、2010年『日本辺境論』(新潮新書)で新書大賞2010を受賞。
 私家版・ユダヤ文化論txt,chm,pdf,epub,mobi下载
私家版・ユダヤ文化論txt,chm,pdf,epub,mobi下载 首页
首页
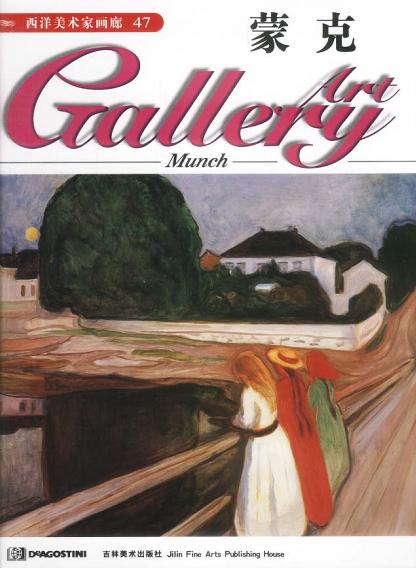


认真看
初中生最应该看的
值得观看的一本好书!
喜欢